
 Librería Perelló (Valencia)
Librería Perelló (Valencia)
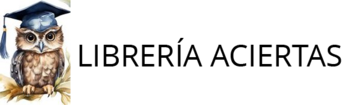 Librería Aciertas (Toledo)
Librería Aciertas (Toledo)
 Librería Elías (Asturias)
Librería Elías (Asturias)
 Donde los libros
Donde los libros
 El AlmaZen del Alquimista (Sevilla)
El AlmaZen del Alquimista (Sevilla)
 Librería Kolima (Madrid)
Librería Kolima (Madrid)
 Librería Proteo (Málaga)
Librería Proteo (Málaga)
世界はひび割れていった。 方程式は、崩れかけた地層の呼吸に触れるには、あまりに乾いていた。 水も、光も、影さえも、そこに留まってはくれなかった。 数式の中で私は重さを測り、流れを計算し、抵抗を求めた。 だが、本当に知りたかったものは、こぼれ落ちるばかりだった。 韓国での日々、コンクリートの曲線と、夜明け前の静けさのなかで、数値は記憶のように変質していった。 地面が音もなく崩れてゆくとき、私もまた、かたちを失っていた。 すでに誰かが書き終えた物語の中に、自分が生きていたような気がしていた。 あるときから、私は見る者になった。 触れられず、語れず、ただ、そこに微かなぬくもりだけが残っていた。 母は、私のノートを開く。 灰を払うように、そっと。 書きはじめる。 文字で私を繋ぎとめようとするように。 私は、その言葉の中で生き続けている。 彼--私を愛した人--は、川へ通う。 黙って座り、かつて吸わなかった煙草をくゆらせ、誰も知らない言葉を呟く。 私には、聴こえている。 物理が教えてくれた。 落ちるものは、すでに落ちているということ。 偶然とは、見えない軌道の名にすぎないこと。 そして、わたしという名の下にあったものは、誰の心にもきちんと残らない、曇った窓の外の景色のようだった。 名前を忘れてしまう日が来ても、内側から音が消えてしまっても、それは、鏡の向こうへゆく途中かもしれない。 怖がらなくていい。 それは、とても自然なことだから。